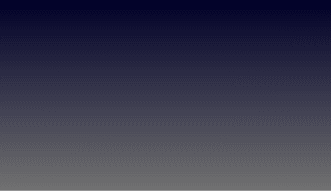余白 鏡面において
(蛇が這う不眠の月光下 盲目の草叢
月面は顔を失う
凝固する夜の黒い宙
星々にばらまかれる神経鏡片
緑苔の鱗くねらせ ガラスの空花瓶は転がったままに)
〈私〉は覚醒し語の石に語らせ語の空いた鎖環を楽々と滑っている と思う
だから午後には再び知らずに問うだろう 無邪気な昼の新月の
薄目をあけた自慰のように
〈犬が鏡に写るだろうか〉と
千切れながら 次の日の昼下がりの上空へ また次の日へ
顔のない新月 白い神経をぶら下げ
不毛の雲を吸った夜の花瓶
何層にも陥没し 暗い唇の竪穴へ
(夜は垂直の虚ろ 押し込めても脳の中で気化する肉声
ガラスを刺す虚像は一瞬の激発だと知るとしても)
水没する水の無音
鏡の中の不眠の夜
覚醒をめざす覚醒の鏡片
欠片 神経の棘 黒い宙に放ち
星のない海を見下ろすために
唇が水平に広がっていくそこでしかない陶酔の水面ではないか
――そうそう 人類の脳天深く (夜の虚ろを埋めようと因斑の松明が染める祝祭の前夜であればこそ)
金緑の蛇が這う 煌く陶酔の波紋に乗り
〈本文抄録〉
2009年刊 A4変形 84ページ 七月堂

堀田展造は亡霊という透明人間(ガラス の 犬) となっ て雨や霧や雪の街を、 三脚も二脚もない 目だけで歩きながら、 亡霊のコ ミュ ニ ケーショ ン の可能性を考え、
「犬語」 なるもの を思い つ い て快感を覚える。 感情の ない 、 自意識もない、 ガラス窓(レ ンズ=目) の感覚から吠える(語る) 犬語(堀田展造の詩語=死語) は人に聞こえず、 理解されず、
したがっ て自分は傷つ かない 。 この 中立地帯の 風景は現実と夢( 夢 現) の 境界、 世界の光を遮っ て影に転化するフィル ム であっ て、 世界の光と影の 表裏を含み、それは生と死の世界の往来自由の 、 両者が重なっ
て両用に転化する半透明の 鏡である。 それは自然の スクリーン で、 雨や雪や靄に触れて濡れると感度が上がり、 外にも内にも浸透し、 世界と脳が反映し合い
、あるい は脳内に映っ た世界の イメージを見るという、 夢見とも、 幻灯の投影像とも見える世界を透かし見、 その 中を歩い てい る。 境界も果てもなく、
その向こ うに死があるとも見えぬ光景はすでに生を越えた彼岸でもあり、 世界の 陰画なの で、 地獄ともい えず、 地上の影と音響と照明が爬虫類や獣や虫となって動き、
朧に光っ てい る。 そこには人間の 言葉や感情がなく、 深夜、 あるい は夜明け前の 透徹した空気がある。 逃げていく先はなく、 残してきた現実に未練もなく、
所属の ない 、 徘徊する姿なき犬は人間ではない が、 言葉を吐き、 並べ て、 意味の ない意味を他者に嗅がせ、 臭跡も残さず消えていく。
人間の気配の ない犬語の 集積は、 詩人という名の 作者を抹消して、 目の 前方か裏側か、 太陽の光や照明に浮ぶ日常の 風景の 表層下、 世界の皮膚の
下に隠れてい る真皮の実像を露にする。
生前でも死後でもない 生の 裏面、 たとえそれが無か虚に見えようと、 その 暗い深淵の上に張っ た薄膜を見てわれわれは平素歩い てい るの
である。 暗い宇宙に浮ぶこ の 地球船も、 明るく光っ ているように見えるが、 太陽がなければじつ は暗い 水と土と石の塊だ。 その上で発する言葉=犬語は太古の遠吠えか。それとも世界の
表層の凍土の 下に眠っ ていて、 夜明けの温もりとともに融け出した太古の森林の ガス かも知れない 。
堀田展造の 言葉は情緒を捨て、 有用を拒絶し、 癒しを求めず、 ゴ ミ捨て場とも廃品集積所とも思える都市の 荒野で、 密かに瞼を開く目をとらえ、
自ら砂となり泥となっ て、 爪跡も残さず彷徨する。 拷問にかけられた罪人がい るわけではない から地獄ではない 。 悦楽も歓喜もない から楽園ではない
。 だが不在の光景の静謐さ、 情念を払拭された透明感は、 神仏はい ない が人間が跡形もなく消滅した無としての浄土とい っ てもよい 。 神の浄めも仏の慈悲もなく、
孤独とい う古代以来の 人間のノスタル ジーもなく、 ただ世界の 陰画を眺める目が 空にあるとい う、 非人称=犬の熟視が表象する都市の原初の 視覚は、 思いがけなく爽やかな空なる気である。 そこ から新生人間の 言葉が呟きとなっ
て聞こ えてくるとき、 無意味の意味を纏っ た言葉の 中に無明の闇を開く目の光が点る。 身体なき言語(犬語) が自らの 目で世界を見、自らの喉を通っ
た声で語るとき、 陰画の世界に原初の 風と声が起きるであろう。
近藤耕人 「透明人間の視る異界」 より

2痙攣する のように
〈私〉は肉体のない死者 のように
夜の寡黙の背骨に滑り込む
もっと壮麗に空洞のシロフオンを奏でようと――
駆け下りる櫛状音階 透過する滑らかすぎる砂嵐
開け放たれた夜の扉から飛び立ち
森を跨ぐ鳥影 眠りへと気化する長い尾の影語たち
執拗な羽音
半音ずれた眠り
〈私〉は寝静まる街角のあらゆる厚みと影からさえ押し出され
脳から剥がれ落ちるたまねぎの影 無明の白樺林の語尾
のように
遠い 重い冬空から落ちた蝶
まだ生温い昼の羽を掻き毟り
痙攣し落下し こ と ば 羽音
沈殿する不眠の落砂 重力を失った地底細音
頭骨の壁に凍ったステンレス針で線描画を描く
遠ざかる唇の翼 鳥影という風景語
触れない語環の空洞
ばら撒かれる無色の石の砂漠
のように
掠れた語の線描画を辿り 明るい不眠の広場にいる きっと
それとも味もない眠りの銀鎖を噛んでいるのだろうか 凍った歯で
脱走する千頭の犬群
押し寄せる海のざわめき 流れ去る波音の際
平らかな夜の水
骨格のすべてを満たし濾過し 塵もなく
軽々と落下し 分散し いずこへ